生徒から被害を聞いた時、適切な関わり方を学ぶ
学校法人常翔学園(理事長:西村泰志)が設置する常翔啓光学園中学校・高等学校(校長:山田長正)は6月6日、同法人の摂南大学(学長:久保康之)現代社会学部で「司法面接」を研究している田中晶子教授を講師に、生徒から被害を打ち明けられた時の接し方を学ぶ教職員対象の研修会を開催します。昨年12月に改正刑事訴訟法が施行され、一定の条件下で、司法面接の録音・録画媒体が証拠にできるようになりました。子供の被害について、身近にいる人が察知した段階で適切に関わることがより重要になったことから、正しい関わり方ができるよう、知識とスキルを身につけることを目的にしています。
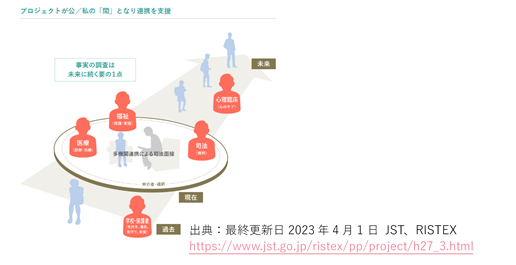
司法面接とは、虐待や事件、事故の被害を受けた疑いのある子供から、事後の対応に生かすために、体験した出来事をできるだけ多く正確に話してもらい、聴き取りにおける負担を最小限にすることを目指す面接方法です。名称は英語の「forensic interview」の翻訳で、「司法的な証拠に足りうる面接」という意味になります。
司法面接は、児童相談所と警察、検察が連携して実施し、専門のトレーニングを受けた代表者1人が原則1回、子供に面接をします。原則1回とする理由は、つらい体験を何度も話すことによって傷付く二次被害を防ぐことや、「記憶の汚染」といって繰り返し話すうちに別の出来事の記憶と混同したり、正確なことが分からなくなったりすることを防ぐためです。
司法面接は現在、年間約2000件実施されています。法務省(2022)の調査によりますと、2018年4月1日から2021年3月31日に判決が言い渡された刑事裁判のうち、司法面接の録音・録画媒体が証拠として採用された件数は35件にとどまっていました。昨年末の改正刑訴法により、今後は採用が増えることが予想されます。しかし、司法面接はまだ一般には知られておらず、被害を察知した時の周囲の対応は課題です。専門的知識のない人が誤った手法であれこれ聴いては、正確な司法面接をすることができなくなってしまいます。

まずは身近なところから司法面接の有効性と、被害者となった子供との適切な関わり方を知ってもらうために、学園内設置校である常翔啓光学園中学校・高等学校と摂南大学が連携し、教職員向けの司法面接について知る教育プログラムの開発に取り組むことになりました。今回の研修会は取り組みの第一歩で、司法面接の概要を知るとともに、子供の権利を守るために被害を打ち明けられた時の望ましい対応を学びます。
田中教授はこれまで、司法面接の面接手法の研究や、児童相談所や警察、検察を対象にした専門職の面接トレーニングに携わってきました。今後は保育園・幼稚園、学校など教育現場での啓蒙活動にも力を入れていきたいと考えています。
日 時:2024年6月6日(木)16:10~17:40
場 所:常翔啓光学園中学校・高等学校(枚方市禁野本町1-13-21)
対 象:教職員 約100人